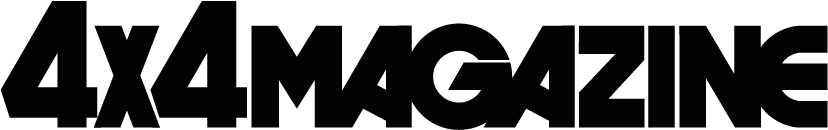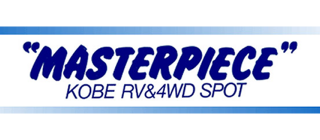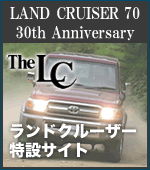オフロード・ドライビング講座 VOL.3
2017.3.25
-

-
四輪駆動車
-
Jeep
-
地形別ドライビングテクニック
さて、今回からは、いよいよ実践的なオフロード走行テクニック編に話を進めよう。本稿は便宜上、地形別あるいは状況別の攻略法解説という形を基本としているが、実際のオフロードでは、これらがきっちりカテゴリー別に現れるわけではなく、多くの場合、いろいろな地形や状況が複合的にミックスされた状態で出現するので、ここで得た知識を応用しながら実践してほしい。
なお、クルマのタイプやサイズはもちろん、仕様、装備等によって走破性能には差があるため、ここで解説している内容が必ずしも最良、あるいは有効とは限らないケースもある。愛車のタイプや仕様に応じた走り方を工夫しながら、より実践的なテクニック習得を心掛けよう。
また、オフロード走行では、アプローチアングル(AA)、デパーチャーアングル(DA)、ランプブレークオーバーアングル(RBOA)と言われるクルマの対地障害角度、いわゆるスリーアングルを意識すると良いだろう。アプローチアングルは前輪とフロントバンパーやフロントシャックルの下端などが形作る角度のことで、この角度が大きいほど前方の障害物に接触する可能性が低くなる。デパーチャーアングルは後輪とリアバンパーやマフラーの下端などが形作る角度、ランプブレークオーバーアングルは前後輪とクルマの腹下部分が形作る角度のことで、アプローチアングル同様に、この角度が大きいほど後方、腹下の障害物に接触する可能性が低くなる。ハイリフト車はこのスリーアングルを拡大することができるので、オフロード走破性を大幅に高められるのだ。
それではさっそく、4×4MAGスタッフカーである’06年式JEEPラングラー(TJ)を中心に、クロスカントリー走行のノウハウを解説していこう。
 ランドクルーザー70バンでは、アプローチアングル(AA)が33度、ランプブレークオーバーアングル(RBOA)が26度、デパーチャーアングル(DA)が25度となっている。
ランドクルーザー70バンでは、アプローチアングル(AA)が33度、ランプブレークオーバーアングル(RBOA)が26度、デパーチャーアングル(DA)が25度となっている。
段差/コブ
ひとくちに“段差やコブ”と言ってもその規模や状態は千差万別。ここでは階段状のギャップを越えるケースを例に解説する。この基本事項を覚えておけば、いろいろなケースに応用可能なのだ。
これらの地形では、そのギャップの高さによっては、直角にアプローチすると腹がつかえてしまうので(ランプブレークオーバーアングルの不足)、斜めにアプローチすると(見かけ上のランプブレークオーバーアングルが拡大する)簡単に越えられるケースが多い。反面、斜めにアプローチするとサスペンションがねじれてタイヤの接地性が悪くなったり、車体が不安定な状況に陥る危険もあるので、どの程度斜めにアプローチするかは、その都度判断が必要になる。
ギャップを越えるときのアクセルワークは「2度吹かし」が基本。1回目のアクセルONで前輪を段差に乗せ、後輪が段差にあたる直前に2度目のアクセルON。この2度のアクセルONをリズミカルにやることで段差をスムーズにクリアできる。
最初のアクセルONでリアが沈み(リアサスが縮み)、その後サスが伸びてくる反動を利用して後輪を段差上に乗せるイメージで二度目のアクセルONのタイミングを図るのがコツだ。アクセルを踏みっ放しだとフロントが跳ね上がりすぎて危険だし、リアサスが縮みっぱなしになるので、サスの反動が利用できない。ここでは、リズミカルなコントロールを意識しよう。
 角度を付けて斜めにアプローチすれば、腹はつかえず、この余裕。前輪が段差に乗ったら一旦アクセルを戻す。
角度を付けて斜めにアプローチすれば、腹はつかえず、この余裕。前輪が段差に乗ったら一旦アクセルを戻す。
 後輪が段差に当たる直前で二度目のアクセルON。リアサスの伸縮をうまく利用するイメージでアクセルをコントロールしよう。
後輪が段差に当たる直前で二度目のアクセルON。リアサスの伸縮をうまく利用するイメージでアクセルをコントロールしよう。
マッドステージ(泥濘地)
泥濘地では勢いをつけて進入し、一気に走り抜けるのが理想。タイヤの溝に泥が詰まってグリップを失ったり、泥に沈んで腹がつかえる前に駆け抜けてしまえばスタックのリスクは減る。しかし、助走のスペースがなかったり、泥の抵抗でそれが不可能な場合もある。そんな時は、アクセルを煽りながら前進を試みる。アクセル踏みっぱなしはグリップを低下させる危険があるので、勢いだけで走破できそうもないと判断した時点で、アクセル開閉にメリハリをつける操作に切り換えよう。
泥が深くタイヤがスリップし出したら、アクセルを戻すことも有効な場合がある。空転しているタイヤの回転を落とすことでグリップが回復する場合があるからだ。実際にはアクセルを煽る要領でオン/オフを繰り返し、グリップする回転域を探りながらコントロールしてみよう。
 前進不可能になったら、後退を試みる。後退が可能なら、前進と後退を繰り返し、少しずつ移動範囲を拡げていこう。
前進不可能になったら、後退を試みる。後退が可能なら、前進と後退を繰り返し、少しずつ移動範囲を拡げていこう。
 こうなってしまうと、マッドテレイン系タイヤでもオンロード系タイヤと変わらない。
こうなってしまうと、マッドテレイン系タイヤでもオンロード系タイヤと変わらない。
ステアリングは抵抗の一番少ない「直進」が原則。ステアリングを切れば切るほどタイヤにかかる泥の抵抗は増えるからだ。しかしこれにも例外はあり、ステアリングを切ることでタイヤがグリップする場所を捕らえてくれる場合もある。ソーイングといってステアリングを左右に素早く切ることでグリップすることもある。
前進が止まってしまったら、いつまでも空転させて接地面を掘ってしまわないことが肝心だ。後退を試みて、可能ならそこから後退と前進を素早く繰り返し、動ける範囲を拡大していこう。そして、前進も後退もできなくなったら早めに諦めてレスキューを待つことも泥濘地走行の基本なのだ。むやみにもがいて地面を掘り車体を泥に深く沈めてしまうと、それだけレスキューも困難になる。“諦めの早さ”も泥濘地走行のポイントと心得よう。
 泥濘地では、ある程度勢いを付けて走り、止まってしまったらムリに回さない…がセオリー。ムリに回して接地面を掘ってしまうと、デフや腹がつかえてレスキューも困難になる。
泥濘地では、ある程度勢いを付けて走り、止まってしまったらムリに回さない…がセオリー。ムリに回して接地面を掘ってしまうと、デフや腹がつかえてレスキューも困難になる。
モーグル地形
スキーのモーグル競技で見られるような左右交互に凹凸が連続する地形、それがモーグルだ。この手の地形では、対角線上にある前後輪が同時に浮きやすく、それによって前進(後退)を阻まれることがある。
4×4には「3輪接地の原則」…つまり、4輪のうち3輪が接地していれば、理論上前進(後退)可能という原則がある。モーグル地形では対角線上の車輪が浮きやすくなるため、2輪接地(いわゆる対角線スタック)となってしまい前進(後退)不可能に陥りやすいのだ。
 右前輪と左後輪が凸面に、そして左前輪と右後輪が凹面にそれぞれ差しかかっている。
右前輪と左後輪が凸面に、そして左前輪と右後輪が凹面にそれぞれ差しかかっている。
 なおも前進すると、左前輪と右後輪が完全に地面から離れた。これがいわゆる“対角線スタック”状態。
なおも前進すると、左前輪と右後輪が完全に地面から離れた。これがいわゆる“対角線スタック”状態。
 左前輪と右後輪が宙に浮いているので2輪接地。どちらかが接地すれば3点接地となり、前進できる。
左前輪と右後輪が宙に浮いているので2輪接地。どちらかが接地すれば3点接地となり、前進できる。
このように、モーグルで対角線上の2輪が空転して進めなくなったら、走行ラインを少し変えて再トライしてみよう。タイヤ1本分ずらした走行ラインではタイヤが浮かず前進できるようになることもよくあるのだ。
お気づきかとは思うが、ここではモーグルでのスタックのメカニズムを解説するため、このようになったが、もちろん、この程度のモーグルであれば、少し勢いをつければ慣性で前進できるので実際はスタックはしない。要は走行ラインを決めるときにこのことを頭に置いておこう、ということだ。
 モーグルへの進入角度を変え、タイヤ一本分脇に走行ラインを取っただけでタイヤが浮かなくなり、前進できるようになった。
モーグルへの進入角度を変え、タイヤ一本分脇に走行ラインを取っただけでタイヤが浮かなくなり、前進できるようになった。
また、冒頭でも述べたとおり、実際のオフロードでは、この手の障害は複合的な要素で眼前に立ちはだかることが多い。つまり、泥の中にこのモーグル地形があったり、段差になっていたりするのがふつうなので、これら複数の基本テクニックの応用が、走破成功のカギとなるのだ。
(つづく)
文/内藤知己
写真/佐久間清人